介護事務に興味があるけれど、「やめとけ」「つらい」という噂を耳にして不安を感じていませんか?
現場のリアルな実情を知らないまま就職して、後で後悔することだけは避けたいですよね。
そこで今回は、現場経験5年の私が感じた「大変さ」と、それでも続けられた理由を本音で語ります。
この記事でわかること
- 「やめとけ」と噂される5つの具体的な理由と対処法
- 居宅と施設で大きく異なる「大変さ」の種類と仕事内容
- 経験者が語る「それでも5年間続けられた」本当の魅力
介護事務の「噂の真相」と「リアルな日常」を知れば、あなたがこの仕事に挑戦すべきかどうかがハッキリと分かります。
目次
居宅と施設で大変さは違う?介護事務の働き方

介護事務の業務内容は、働く事業所の種類によって大きな違いがあります。
| 種類 | 対象(該当する事業所の種類) | 請求内容 | 請求の複雑さ |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス | 自宅で生活している利用者 (訪問介護、通所介護など) | 提供されたサービス内容や回数を個別に集計して請求 | 高い |
| 施設サービス | 施設に入所している利用者 (特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど) | 介護度に応じて一律の定額を請求 | 低め |
居宅サービスでは、サービスごとに単位数や加算要件が異なり、個別対応が求められるため請求内容が複雑です。
加算の条件や利用回数によって毎月の内容が異なるため、事務側の確認作業も多く、ミスのない入力が求められます。
一方で施設サービスでは、利用者の介護度によって請求内容が定額で決まっているケースが多く、月ごとの変動が少ないためルーチン業務になりやすく、請求処理にかかる負担も比較的軽くなります。
私は訪問介護を中心とする居宅サービス事業所で事務職として勤務していたため、サービス内容や請求方法をその都度確認しながら対応する必要があり、常に緊張感を持って仕事に臨んでいました。
このように、事業所のタイプによって業務負担や大変さは大きく変わります。
「自分に合った職場」を見つけることが、介護事務を長く続ける一番のコツです。
特親身なサポートで評判の『ジョブソエル』なら、職場の雰囲気や業務内容を詳しく把握しているため、あなたにマッチした働き方を提案してくれます。この記事も参考にしてみてください!
大変なことも多い?介護事務の主な仕事内容

ここからは、居宅サービスでの介護事務の主な業務をご紹介します。
介護事務の仕事は多岐にわたっており、単純な書類作成や電話応対だけではありません。
請求業務やスタッフの勤怠管理、利用者への対応、その他事業所運営に関わるあらゆる業務に携わることになります。

ここでは実際の現場で経験した具体的な仕事内容を交えて、介護事務の全体像をより詳しく掘り下げていきます。
介護報酬請求(国保連へのレセプト業務)
介護報酬請求の中心となるのが、国保連(国民健康保険団体連合会)へのレセプト提出です。
これは毎月10日までという期限があり、それに間に合わせるために前月のサービス提供内容を正確に集計・確認しなければなりません。
提出するデータに誤りがあると、審査で差し戻されることがあり、再提出の手間が発生します。
この請求業務で得られる報酬は、事業所の主な収入源であり、経営の安定に直結する非常に重要な業務です。
つまり、介護事務員が行うレセプト処理の正確さが、そのまま事業所の売り上げに影響を与える責任ある仕事だと言えます。
また、これらの業務では「伝送ソフト」や「請求ソフト」など専用の業務ソフトを使用するため、基本的な操作に慣れるまでに時間がかかるのも特徴です。
細かな入力作業が続くため、集中力と正確性が求められます。
ご利用者負担分の請求
介護サービスの費用のうち、国保連に請求する部分とは別に、利用者が自己負担する金額があります。
この負担割合は所得に応じて1割から3割と異なり、それぞれの負担額に応じた請求をしなくてはなりません。
請求額が確定したら、利用者に請求書を作成・送付し、支払い方法に応じて引き落としの手続きや振込の確認、現金での受け取りなどを行います。
利用者によって支払方法が異なるため、個別対応が必要です。
中には請求内容について問い合わせをされる方や、ご家族からの確認の電話がある場合もあります。
そのため、正確な対応と丁寧な説明力も求められる業務の一つです。
勤怠や労務のサポート
介護事務の業務には、現場で働くスタッフの勤怠管理や労務に関するサポートも含まれる場合があります。
具体的には、スタッフが提出する勤務表を取りまとめ、出勤日数や勤務時間、有給休暇の取得状況などを集計します。
有給の残日数や申請状況を正しく把握し、適切な管理を行うことが重要です。
また、実際の給与計算は外部の経理担当や本部が行う場合もありますが、事業所内で勤務表のチェックや勤務実績の入力、明細の確認など、給与計算の補助業務が求められることもあります。
勤怠や労務のサポートは、スタッフとの日々のコミュニケーションも欠かせません。
現場のスタッフが安心して働けるようにサポートする大切な役割の一つです。
来客・電話対応
窓口対応では、利用者やそのご家族、医療関係者、ケアマネジャー、訪問看護師などさまざまな方が事業所を訪れます。
介護事務はそのような来訪者に対して第一に対応する役割を担っており、事業所の「顔」として丁寧で迅速な応対が求められます。
特に施設系の事業所では、面会者や見学者の対応も含まれるため、受付から案内、応接まで幅広い対応が必要です。
また、電話対応も介護事務の重要な業務の一つです。
電話の内容は介護保険や医療に関する専門的なものであることも多く、専門用語が飛び交うことも珍しくありません。
そのため、わからない言葉があった場合は曖昧にせず、必ず確認する姿勢が大切です。
現場スタッフが外出している時間帯や対応中の場合には、事務員が代わりに要件を聞き取り、伝言を預かったり折り返しの連絡を調整したりする必要があります。
一般事務・雑務
介護事務の業務の中には、日常的な書類の作成やファイリング、関係機関への文書送付といった事務処理も含まれます。
これらの業務は、記録の整備や業務の効率化に欠かせない重要な役割を果たしています。
また、備品や消耗品の発注業務、届いた郵便物やFAXの仕分けなど、事務所内で必要とされる物品の管理や流通に関わる仕事も担います。
さらに、事務所内の簡単な清掃を行ったり、ゴミ出しを担当することもあり、職場を快適に保つための雑務にも携わります。
施設や事業所内での行事やイベントの際には、飾り付けや備品準備、お茶出しなど来客対応も行うことがあり、状況に応じて幅広い業務を柔軟にこなす力が求められます。
介護事務は「やめとけ」と言われる理由…つらいと感じる5つのポイント

ここからは、介護事務の仕事を実際に経験する中で「つらい」と感じた点を5つご紹介します。
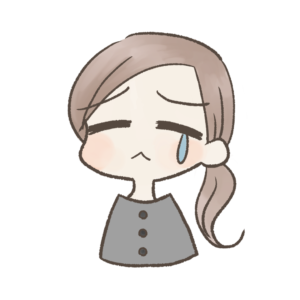
事務職といっても、一般事務ではなく介護業界ならではの専門性や業務の幅広さがあるため、
思っていたより大変と感じることもあるかもしれません…
事前に知っておくことで心構えができ、実際の現場で戸惑わずに対応できるようになります!
1. 月末月初は繁忙期
毎月10日が介護報酬請求の締切日であるため、月末月初はどうしても業務が立て込みます。
特に前月分のサービス内容を確認・入力・チェックする作業に加えて、ご利用者への請求書発行や支払い手続きも重なるため、非常に忙しくなります。
さらに、同時期に給与計算や勤怠チェックといったスタッフ向けの処理も必要になることから、気がつけば残業や休日出勤が増えていた、ということも。
こうした理由から、月末月初に休暇を取りにくいという声も少なくありません。
2. 制度理解が必要で最初は難しい

介護保険制度や報酬の仕組みは非常に複雑です。
サービスの種類や加算条件、利用者の要介護度に応じた単位数の違いなど、覚えるべき情報が多く、特に未経験から始めた方には最初の壁となります。
用語も独特で、「居宅」「施設」「区分支給限度額」など、聞き慣れない言葉に戸惑うことも多いでしょう。
ですが、月々の業務をこなしていくうちに自然と知識が身につくため、最初の数カ月は「覚える期間」と割り切って取り組む姿勢が大切です。
3. 金銭を扱うプレッシャー
介護報酬請求や利用者への請求業務は、事業所の経営に直結する重要な仕事です。
請求ミスがあると、国保連からの入金が遅れたり、ご利用者に誤った金額で請求が届いたりと、トラブルの元になります。
そのため、一つひとつの確認作業に神経を使う必要があります。
責任の重さにプレッシャーを感じることもありますが、最近ではチェック体制が整っている事業所も多く、複数人でダブルチェックを行う環境が整っている場合もあります。
介護報酬請求業務は各事業所が責任を持って行うべき業務であるため、事務員だけが責任を負う必要はありません。

一人で抱え込まないことが大切です!
4. 高齢者とのやり取りに戸惑うことも
介護事務員は、電話や窓口で高齢者と直接対応する機会が多いです。
その際、耳が遠く会話が聞き取りにくい方や、認知症の影響で話が噛み合わない方などへの対応に困る場面が出てきます。
特に電話対応では、相手の表情や動きが見えない分、状況を読み取るのが難しく、何度も同じ話を繰り返されたり、伝言が正確に伝えられないなどのストレスを感じることも。
ただ、丁寧に、焦らず、繰り返し説明する姿勢があれば徐々に慣れていくものです。
5. 時には現場業務を頼まれることも
介護事務の主な仕事は事務所内で完結しますが、事業所によっては現場が人手不足の際などに、利用者の見守りや配膳、送迎時の対応など軽い現場業務を頼まれるケースもあるようです。
デイサービスや小規模事業所では、スタッフが少人数のため、事務員も柔軟な対応を求められやすい傾向があります。
介護経験がない方にとっては、身体介助まではないにしても、心理的な負担や戸惑いを感じることがあるかもしれません。
事前にどの程度の現場対応があるのかを確認しておくことが安心材料になります。
それでも続けられる!介護事務の魅力

介護事務の仕事には確かに大変な面もありますが、それ以上に続けたくなる理由ややりがいがたくさんあります。
このセクションでは、実際に働いて感じた介護事務の魅力についてお伝えします。
専門知識が身につき、自分の市場価値が上がる
介護事務の仕事を続けることで、介護保険制度や報酬請求に関する実務的な知識が自然と身につきます。
これらの知識やスキルは、業界内での専門性として評価されるポイントとなり、転職やキャリアアップの際にも大きな武器になります。
特に、介護請求ソフトの操作や国保連へのレセプト作成といったスキルは、他の事業所でも即戦力として重宝されやすいのが特徴です。
積み重ねた経験がそのまま“市場価値”につながるため、働きながら成長を実感できる点も大きな魅力です。
事務職でも人と関わる機会が多くやりがいを感じる
事務職というと内勤で淡々と作業をこなすイメージを持たれがちですが、介護事務は多くの人と関わる仕事です。
利用者やその家族との窓口応対、ケアマネジャーや医療関係者との連携など、日常的にコミュニケーションの場面があります。
人との関わりが好きな方にとっては、単なる事務仕事以上の充実感が得られるはずです。
また、直接「ありがとう」と声をかけてもらえる機会があるのも、介護事務ならではのやりがいです。
誰かの役に立っているという実感を持てることが、仕事のモチベーションにもつながります。
長く働きやすい仕事
介護事務は体力的な負担が少ないため、年齢を重ねても長く続けやすい職種です。
特に女性にとっては、家庭や子育てとの両立がしやすい点もメリットです。
また、経験を積んだベテランの事務員は職場にとって貴重な存在であり、年齢に関係なく活躍の場があります。
中高年から介護事務の仕事を始める方も多く、再就職先としても人気があります。
柔軟な勤務形態を取り入れている事業所も増えており、ライフスタイルに合わせて働き方を選べる点も長く働ける理由のひとつです。
介護事務はつらいだけじゃない!やりがいのある仕事です

介護事務の仕事には確かに「大変な面」があります。制度の理解や金銭管理など、責任が重く感じる場面も少なくありません。
しかし、介護事務は社会に必要とされる存在です。介護の現場を支える縁の下の力持ちとして、やりがいや成長を実感できる仕事です。

未経験でも、前向きに学ぶ姿勢があればきっと続けられます。
「介護に関わる仕事がしたいけれど、現場は体力的に不安…」という方は、ぜひ介護事務という選択肢を検討してみてくださいね。
スキルアップを目指す方は、資格取得にチャレンジしてみるのも一つです。
「現場に出てから覚えるのは不安…」という方は、事前に資格を取得して基礎知識をつけておくと、働き始めた時の負担がグッと減ります。以下の記事も参考にしてみてください!







